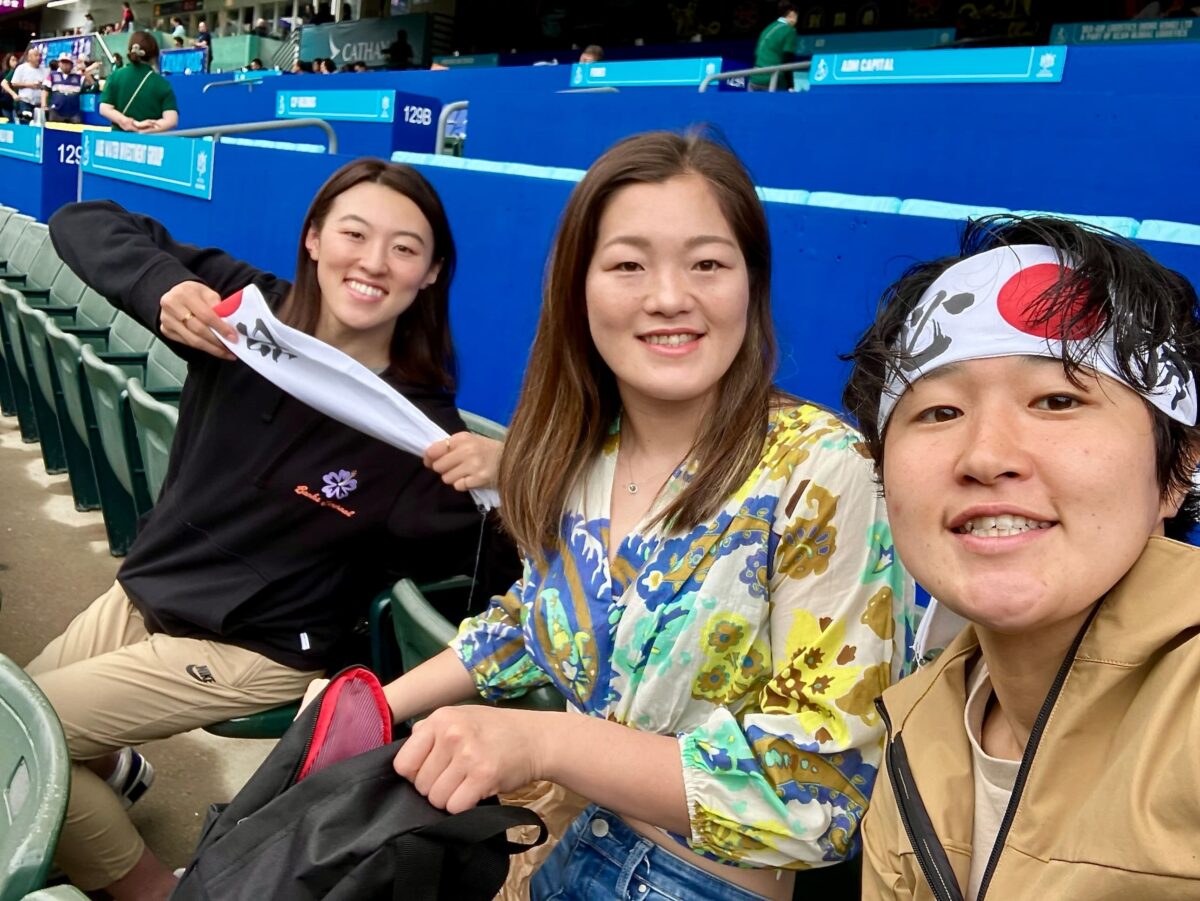Keyword
大分。九州ではあるのだが瀬戸内の西の端とも解釈できる。宮崎や鹿児島とはやはり異なり、4月がそこまで近づいても案外冷える。
3月30日。クラサスドーム大分。ここをセカンダリーホストとする横浜キヤノンイーグルスとトヨタヴェルブリッツが対戦した。前節はともに土がついて、両者、踏ん張りどころだ。
17-29。イーグルスは星を落とした。数学的にはともかく、心理においては6位までのプレーオフ進出をにらんで、いかにも苦い。
開始前。中継のJ SPORTSが両監督(ヘッドコーチ)の会場到着の一言をもらっている。イーグルスの沢木敬介監督はいつもの鋭い表情でこんな内容を述べた。
「自分たちのスタイルをやり抜く」
では横浜流とは。すぐ浮かぶのは、よく組織され、準備され、ハンドリングやランのコースのスキルに裏打ちされた能動的アタックである。多彩なパスが通って観客にはうれしい。
本日も貫こうとした。36歳の10番、田村優のパスやキック、間合いの詰め方はことごとく「違い」をもたらす。名人の手と足より繰り出されるボールはみずからの意志が存在するかのように、無理なく、絹の手触りのまま目標へ収まる。
なのに開始34分までイーグルスのスコアは記録されなかった。陣地の中盤、トヨタがキックに備えて2~3人を後衛に配する状況ではアタックは機能する。だが敵陣22m線内に侵入すると15人の緑の壁を崩し切れない。
そのことは現代のラグビーの典型でもある。よって重用されるのが「問答無用型」のペネトレーター、人間砕氷船である。
この日、イーグルスはナンバー8のアマナキ・レレイ・マフィを欠いた。シオネ・ハラシリも第5節を最後に負傷で不在だ。
大分での8番はビリー・ハーモン。マオリオールブラックスやハイランダーズの主将を務めた。個人的には、負けたチームながら当日の最優秀選手である。タフでスマートでハードでスキルフル。ただし砕氷船ではない。この人が6番に回れたら、ヴェルブリッツはもっと困ったかもしれない。ボールを動かす集団に「壊して砕く」が適所を得てまざると相手はおそろしい。
以下は古き時代の戦法構築の流れ。体の分厚い突破役がいない→個の強さに頼らずボールを理詰めに運ぶスタイルを築き上げる→不在が必要を招き、そこで勝負するほかないので反復はなされ、熟練へ近づく。
現在のファーストクラスのゲームはその方法だけでは結果を残せない。パスを駆使、スペースを創造しつつ前進をかなえても、いよいよトライラインに迫れば肉弾総力戦を求められる。
イーグルスはなかなかトライを奪えない。それでも、なんとか勝利のイメージは浮かんだ。すなわち。得点に結ばれなくとも球を保持することでトヨタの守りの脚を削り、おしまいの20分から大いに振り回す。

ところが、ここまで2勝、白星につれなくされたヴェルブリッツは5-7で迎えた後半の2分、14番、ジョセフ・マヌがスコアするなど本来の決定力を示した。なにより防御の統制をなくさなかった。
試合後、クラブの関係者がささやいた。
「佐々木隆道がディフェンスを整えています」
早稲田大学のシーズン終了後、移ってきた腕利きコーチの名を挙げた。
余談、この人、ササキとは呼ばれない。なぜかフルネームでササキタカミチとみんなが言う。もうひとつ余談。本稿筆者の知人である楕円球好きの元仏教総合雑誌編集長は昔、よく話していた。
「ササキタカミチが現役を引退したら独占インタビューするんだ」。佐々木隆道の生家は大阪のお寺なのである。ジャージィを脱いだら住職になると勝手に決めて、ひとりでにやにやした。
熱戦は終わり、小さな旅が始まる。大分駅へ戻って、朝の散歩で目をつけた定食屋「大納言」を襲おう。標的は肉にら定食。あら、貼り紙が。「本日は夜の営業をお休みします」。ならば、これも狙いを定めた「留園」のホイコーローか。なんと、こちらも臨時休業ではないか。
長くラグビーを追ってきたので、この程度では動揺しない。モールを押し切れないならプランB発動、サイドを複数でえぐる。それもダメなら、ラックをもうひとつ軽快に刻んで、9番の背にひそむショートサイドのWTBがいきなり出現、短いパスでトライラインへ(これはよく抜ける)。
と、慣れぬ土地に思案をめぐらせていると、ありがたい、ふたりの「同僚」がいろいろ助けてくれた。どうりょう。職場や役目が同じ人。なぜカッコでくくったかといえば、さっき初めて一緒に働いたからだ。
地元の大分大学ラグビー部の若者が実況放送の記録集計を担ってくれた。初対面でいきなり質問した。「大分大学の略称は?」。「ブンダイです」。いいなあ。ちなみに長崎大学はチョウダイ。
ともにバックスである。姓のイニシャルはそろってY。徳島県立城東高校と大分県立大分雄城台高校の卒業生だ。ブンダイ、部員数は? 両Y君の声がそろった。
「いつも15人ぎりぎり。新入生が何人きてくれるかです」

はたして経験者をキャンパスで捕捉できるか。見つけられたら、こんどは「説得です」。年長の人類として助言する。「ひとり、経験のある1年生が見つかったとする。多数で囲んではならない。こっちもひとりだ。熟慮選考を経た説得のエースがそっと近づく」。もしくは、ふたり。その場合、片方が切れるタイプなら、いくらか抜けたところのある部員を組み合わせる。勧誘のスパイスは愛嬌である。
人間は「ひとりの本気」に感応する。5人での説得なんて強制みたいなものだ。と、えらそうに諭すうちに、大分大学のラグビー部に誘われる新入生をうらやましいと思った。だって人生、「お前がいてくれないと困る」なんて、会ってほどない他者に懇請される経験はまれだろう。
請われたら飛び込んでみる。人情の話ではない。おのれの可能性のストーリーである。新しい環境にあって自分では気づいていない能力が予期せず引き出される。
高校の元ラグビー部員よ。新しい進路先、無作為抽出順不同で、たとえば学習院大学、桃山学院大学、弘前大学、京都工芸繊維大学、上智大学、日本福祉大学、駒澤大学、もちろん、わがブンダイ、それぞれの熱烈歓迎に乗っかって、えいっと飛び込んじゃえ。
必要とされぬ者はひとりもいない。そんな集団とめぐりあえた。部員120人の強豪クラブで競争と共感を両立させようともがく青春と同じだけ幸運だ。