
日本ラグビー協会。ニュージーランド・ラグビー協会。狛江市ラグビー協会。スコットランド・ラグビー協会。モンゴル・ラグビー協会。沖縄県ラグビー協会。
あまた協会はあれど、ただ「ラグビー協会」と称するのはひとつだ。「THE RUGBY FOOTBALL UNION(RFU)」。このほど来日のイングランドの統括団体である。
いちばん最初なので、わざわざ「イングランド」と示す必要はなかった。すなわちラグビーの母国。愛用の古い広辞苑で「ぼこく【母国】」を引いてみた。
「①分れ出た国から、もとの国をいう称」。素敵な語釈だ。なるほど本来の母国とは他国がそう呼んで成立するのか。
1871年。ラグビー協会創立。同年、スコットランドとの最古のテストマッチは行なわれた。それから59年後の1930年、昭和5年、初めての日本代表が編成され、カナダへ遠征する。6勝1分けの好成績を収めた。
創成期の日本のラグビー人はイングランドを恋い慕った。1929年には盛んにRFUと同国への遠征について交渉している。どうやら、つれなくされた。
以来、片思いを続け、悲しくもグラウンドでなく戦場で先にぶつかり、ようやくラグビー協会創立100年の1971年、イングランド代表(XV)の日本ツアーは実現する。双方ノートライで桜のジャージィは惜敗、語り草の「3-6」である。
ちなみに「XV 」とは「フィフティーン」。アマチュア期、新興勢力との国際試合を伝統協会はキャップ対象とせず、実質のナショナルチームをそうくくった。悔しいといえば悔しい。現在の規範に照らせば正代表である。
公正を問われる時流、おそらく近い将来、過去のジャパン戦出場者にもさかのぼってキャップを与えるようになるだろう。実は日本協会にもアジア諸国との多くの試合をテストマッチとしなかった苦い史実がある。一刻も早く、キャップ0の功労者に授与式を。
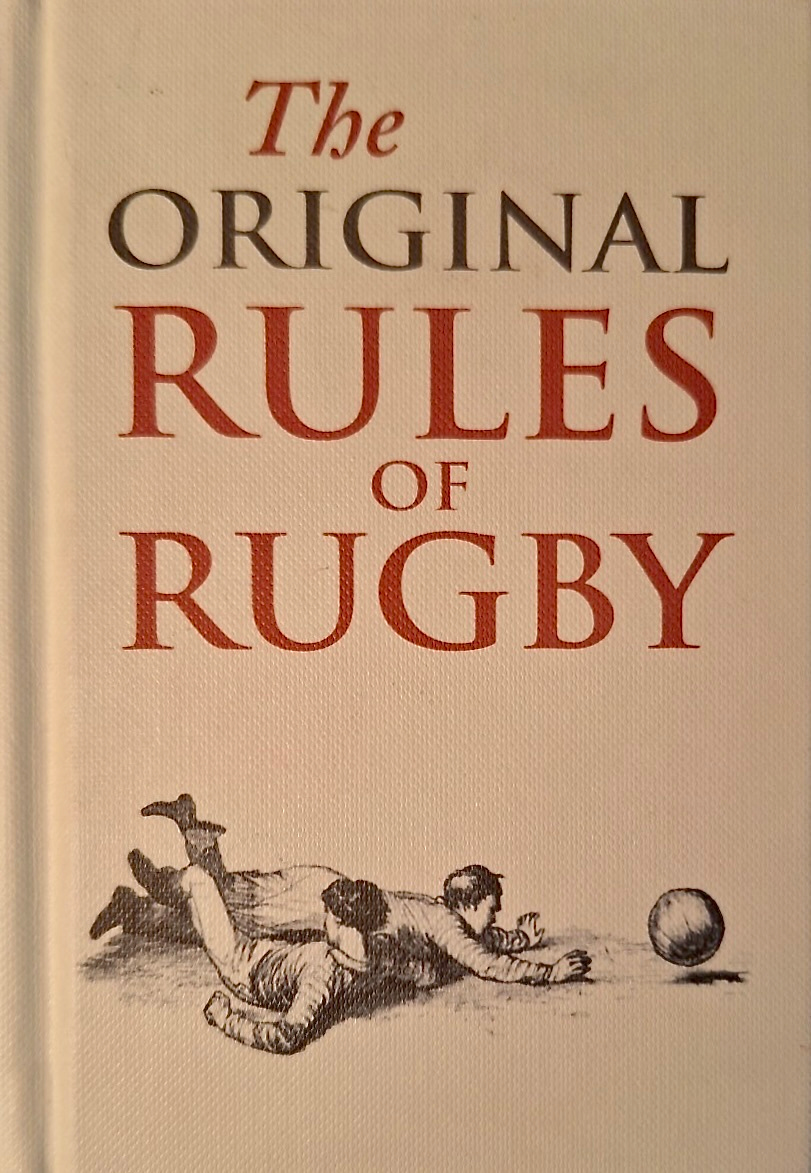
さてイングランド。その代表をひいきにしようが憎たらしく感じようが、いずれにせよ特別な響きだ。ひとつの理由はエリス少年のストーリーにある。想像をかきたて、微笑も誘う、かの忘れがたい物語の発祥の地なのである。
おさらいしよう。
1823年。某月某日としかわからない。日本は文政6年、シーボルトがやってきて、勝海舟の生まれた年である。
イングランドのラグビー校のグラウンドをウィリアム・ウェブ・エリス、いまワールドカップのトロフィーに名を残す16歳の少年が手でボールをつかんで走った。これをもってラグビー競技の起源とされた。後世のスポーツを豊かにさせた「ルール破り」である。
親愛なるJust RUGBYの読者には自明だろうが、かつて流布した「サッカーの試合中に」はあやまりである。あのころはサッカーもラグビーもなかった。「校内ルールのフットボールのさなかに」が正しい。当時、ボールを拾い上げる「ランニング・イン」は反則であった。
ここまでが伝説である。
本コラムの筆者は1997年にラグビー校を訪ねた。みんながするように芝の上に片膝をついてみた。エリスの記念碑があって、そこには「あっぱれなルール破り(FINE DISREGARD)」と刻まれていた。
では本当に「あっぱれ」だったのか。あやしい。「エリス、走る」が初めて明らかとされたのはルール破りの57年後、1880年である。考古学愛好家のマシュー・ブロクサムという人物がラグビー校の校友会誌に発表した。ただし本人はエリスの入学時には卒業しており見たわけではない。
1895年になって同校の卒業生組織が調査を始めた。
「1830年代にプレーした者はひとつの点で同意した。誰もエリスの名を聞いたことはない」(ガーディアン)
ただしトーマス・ハリスという元在校生は5学年先輩にあたるエリスを覚えてはいた。そのうえで「彼の名を(競技の起源の)権威として引くべきではない」と記し、1828年の段階では「ボールを手に持つことは明確に禁じられていた」(いずれも同前)と明かした。
昨年、スプリングボクスの面々がパリの夜空へ差し上げた優勝杯の「権威」は確かなのか、いささか心配になる。
されど歳月を重ねて事実をはみ出す余白もまた文化だろう。「実際に起きなかったことも、歴史のうちである」(『寺山修司の仮面画報』)。権威に従順な者によってラグビーが誕生するよりはうんと愉快だ。
のちに聖職者としてフランスに没する少年エリスの(幻かもしれぬ)ランから201年の6月22日、その(もしかしたら)末裔が東京の国立競技場へ現れる。
新体制のジャパンは、どうか昨年のワールドカップの対イングランド、開始7分35秒の一幕を思い出そう。
敵陣コーナー近くでエリオット・デーリーをタッチラインの外へ押し出す。速攻を許すまいと、胸に薔薇の11番はボールを少し転がした。SHの流大がこのささやかなズルに突っかかり、背を突き飛ばした。いいぞ。怒ったのでない。怒ってみせたのだ。
世界ランクはこちらが下でも一歩も引かない。あれは「分れ出た国」の「もとの国」への闘争宣言だった。


